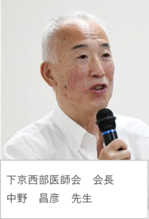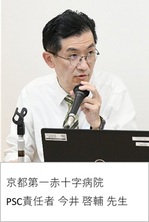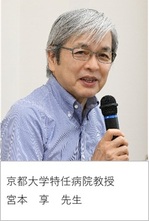新着情報
新着情報
令和7年7月12日「医師会・一次脳卒中センターによる「脳卒中地域連携の会」を開催しました。」
京都市中南部エリア(中京区・下京区・南区・東山区)における脳卒中対応力の向上をめざす「脳卒中地域連携の会」が2025年7月12日、下京区の康生会武田病院で開催されました。主催は京都におけるCブロック一次脳卒中センター4施設で、参加対象となったのは京都府医師会会員、回復期リハビリテーション病院・一次脳卒中センターの医師・コメディカルです。当日は53名もの参加者が駆け付け会場は満杯となり、白熱した議論が交わされました。
冒頭、康生会武田病院PSC責任者の滝和郎先生(総合司会)が開会を宣言。「今回は京都市南部の一次脳卒中センターである、京都市立病院、京都第一赤十字病院、京都九条病院、康生会武田病院の共催で行います。これに加え、京都府医師会、中京東部、中京西部、下京東部、下京西部、東山の各地区医師会のご後援をいただき、大変、感謝しております」と謝意を表明しました。
その後、下京東部医師会会長の前田眞里先生が登壇。連日の猛暑に触れながら、「これだけ暑い日が続くとストローク(脳卒中)の可能性が増加します。中京区・下京区・南区・東山区の我々医師会と病院の先生方が連携することで、脳卒中発症後の患者さんをこれまで以上にサポートできるよう、脳卒中地域連携の会を盛り立てていきたい。頑張って勉強いたしましょう」と開会挨拶を行いました。
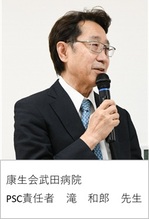
セッション1は、京都第一赤十字病院PSC責任者の今井啓輔先生が座長を務め、京都大学特任病院教授の宮本亨先生が「脳卒中生活期における連携体制とかかりつけ医登録」と題し講演を行いました。
宮本先生は、「従来から連携主治医制が提唱されていますが、『なんとなく紹介状を書き、処方をお願いします』という形になりがちです。これに対し、『脳卒中生活期における連携主治医制』は、医療ソーシャルワーカー同士が中心となり、急性期、回リハ、かかりつけ医など関係施設、患者さんも含めしっかりと情報共有を継続していくのが特徴です」と独自の運用スタイルを解説しました。
セッション2は、京都市立病院PSC責任者の中谷嘉文先生が座長を務め、青木医院院長の青木淳先生が「生活期かかりつけ医について」と題し講演しました。
青木先生は講演の冒頭、脳神経外科医の開業後の役割について「脳卒中の一次予防・二次予防、軽症例のセカンドオピニオン、生活習慣病の管理(脳卒中再発予防)、認知症の予防、そして高齢者の健康管理、在宅診療、看取りなど多岐にわたります」と説明しました。
青木先生は、「地域医療全体で包括的な医療体制を構築することが重要です。シームレスな医療提供体制を構築するため、『脳卒中生活期かかりつけ医』への登録を」と会場に向かって呼びかけました。
質疑応答では、森一樹先生(京都新町病院)が「この『かかりつけ医』は『神経内科医や脳神経外科医がやるもの』といった認識が一般的のようですが、実際、登録資格はどういった認識でしょう」と問いかけると、青木先生は「そこがハードルを高くしてしまう要因です。脳卒中はやはり循環器病で、実際に来られる患者さんの多くは循環器に問題があります。リスクファクター管理が大切なので、我々脳外科医よりむしろ循環器の先生方の方が良いと感じています。やはり、広く多科の先生にご参加いただくことが望ましい」と考えを説明しました。

セッション3のテーマは「かかりつけ医との意見交換」です。今井先生と中谷先生が司会進行を務め、各医師会の5人の先生方が発言しました。
中京東部医師会の林理之先生(はやし神経内科)は、「高齢化でサービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームが普及しています。これらの入居者の対応(協力医療機関)は、いわゆる『チェーン店化』した訪問診療によるケースが多い。地域とのつながりのない先生方による訪問診療は、当会で議論されるような共通認識が通じません。これをどうやってカバーしていくのかが、今後の課題として残るのではないでしょうか」と指摘しました。
中京西部医師会副会長の森一樹先生(京都新町病院)は、回復期病院で発生した急性期脳梗塞の事例をあげながら、「私は元救急医です。中小病院の多くで発症から画像撮影・診断までにかなりの時間がかかっていることを知り、ショックを受けています。医師の平均年齢が高い施設もありますが、どのような病院であれ全ての医師に初期診療の知識・スキルが必要であると考えています。これをどうやって普及していったらいいか頭を悩ませています」と胸中を明かしました。
下京東部医師会の冨井康宏先生(冨井医院)は4つの課題があるとし、「まず『予防しているのは脳卒中だけではない』ことです。次に、急性期に搬送された結果がなかなか伝わってこず『病態把握が難しい』ことです。また、脳卒中の生活期をゴールと考えられての紹介が少なくありませんが、私はこれをスタートと考えています。多職種で関わりながら良いスタートを切れるようにしたい。最後は『就労継続できないこと』です。お一人おひとりに適した就労支援をしていきたい」と説明しました。
下京西部医師会の青木淳先生(青木医院)は、「循環器やがんは、専門医とかかりつけ医(開業医)が双方向で治療しているイメージです。ところが脳卒中では、かかりつけ医とともに急性期を担当した先生が診療するケースが少なく、双方向的な診療が欠けているのではないでしょうか」と問題提起しました。
東山医師会会長の手越久敬先生(手越医院)は、「一般内科で生活習慣病・慢性疾患を中心に治療しています。通院患者さんにいつもと違う症状が出たときに紹介させていただくのですが、そこで何が起こっているのか、緊急性はあるのかが重要です」と実際の紹介事例を披露しました。「我々、非専門のかかりつけ医からすると、必要時に専門医・専門の診療科につながる体制が何より重要で、それは患者さん・ご家族の安心ともなります」と考えを述べました。
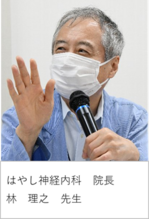


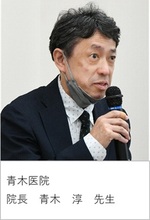

セッション4のテーマは「各職種会議からの報告」です。京都九条病院PSC責任者の平井誠先生が司会進行を務め、中村祐司先生(京都九条病院副看護部長)、林千麗先生(康生会武田病院薬局長)、大場寿惠先生(京都第一赤十字病院リハビリテーション科課長)、西山友香先生(京都市立病院ソーシャルワーカー)がそれぞれの立場から発言を行いました。
下京西部医師会会長の中野昌彦先生は、視床出血の治療後、在宅リハビリを行っているケースのエピソードを披露し、「私も脳卒中連携に大変お世話になっている一人で、この登録医制度を支持しています。
医歯薬介護がしっかりと連携することが重要ですので、どうぞよろしくお願いします」と登録を呼びかけました。