 新着情報
新着情報
令和7年3月6日「循環器領域 地域連携セミナー」を開催しました。
-最新の治療技術を共有し、適切なコンサルトについて意見を交わす-
「循環器領域 地域連携セミナー」が2025年3月6日、下京区の京都タワーホテルで開催されました(康生会武田病院、下京西部医師会、京都循環器医会、ノバルティスファーマ株式会社、大塚製薬株式会社:共催)。
セミナーは3つのセッションで構成。オンラインと会場によるハイブリッド方式で行われ、参加者は症例をベースに様々な意見交換を行いました。

開会挨拶で康生会武田病院の武田純院長(下京西部医師会副会長)は、「当院は2006年から20年近く地域医療支援病院として、ご紹介への対応、24時間体制での救急医療の提供、医療機器や技術の共有、講演会・研修会など、最新の医療技術等の情報をご提供することなど、その役割を果たしてきました。この主旨にのっとり、本日は不整脈や心不全など循環器領域での当院の体制・技術について、アップデート情報をご紹介させていただきます。皆様方の明日以降の診療に寄与し、また連携がさらに深まる1日となることを期待しております」と述べました。
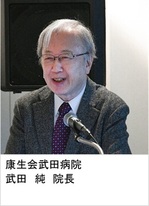
セミナーは高宮内科クリニックの高宮充孝院長が座長を務め、セッション1では康生会武田病院不整脈センターの垣田謙センター長が「最新の心房細動治療の実際」と題し講演しました。
垣田センター長は肺静脈隔離について、「いわゆる職人的な技術が必要であったり、他の臓器・神経を熱で傷つけてしまう合併症などが課題でした。この解決のため、様々なデバイスが開発されてきたのです」とし、冷凍バルーンやレーザーバルーンなどを紹介しました。「ただ、これらはいずれもサーマルアブレーションと言われ、熱が上がる・凍らせる治療で、他臓器への影響が少なからずありました。そうしたなか、熱を全く出さないエナジーソースの"パルスフィールドアブレーション(PFA)"が登場しました。PFAは、アポトーシスを起こす電界をつくることで自然に細胞死を起こす治療法です。心筋細胞だけに影響し、裏に通る食道や反回神経にエネルギーは伝わらないのです」と動画を使って仕組みを説明し、同院での実施状況を語りました。
また垣田センター長は、"心房細動"についてイメージ図を示し、「40代、50代で発症された方は、そこからの人生が長くあります。そのまま生きていくには道が険し過ぎます。一度アブレーションで心不全の重荷をとってあげると、色々な治療の選択肢が産まれ、その時々にテーラーメードな治療を行うことができます」とし、会場に向かい、「我々は、かかりつけの先生とご相談させていただき、一緒に治療を進めることが重要だと考えています。"一度、治療についての話を聞いてみては?"と患者さんに仰っていただければ、いつでも対応させていただきます」と呼びかけました。


セッション2は、康生会武田病院循環器センターの宮井伸幸副部長が「末梢動脈疾患治療戦略」と題し講演しました。
宮井副部長は末梢動脈疾患のなかでも下肢閉塞性動脈疾患(LEAD)について、「我が国の患者数は40万人程度と推測され、無症候性のものを含めると50~80万人の患者群がいると言われています」と疫学データを紹介。「とくに当院が重きを置いているのがカテーテル治療です。どのように血管を広げるか、どのようにそれを維持するかの2点を考えています」と、領域別の治療方法や適したデバイスについて、それぞれの成績データ交え紹介しました。
この一例として宮井副部長はVIABAHN VBX Balloon Expandable(ゴア社)を挙げ、「これは人工血管を内側に貼ったステントで、金属だけのものより開存率はさらに高いものとなっています。それなら全例これを使えば良いという話になりそうですが、タスクC・Dの複雑病変のみの適用となっています」とし、その注意点とともに、右の総腸骨動脈の閉塞病変への実施症例を、動画を用いて解説しました。
また宮井副部長は「非致死的心血管イベントは20%ほど認め、死亡された患者のうち心血管イベントを75%に認めた」とLEADの自然経過を表で示し、「当センターでの、依頼されたABI(足関節上腕血圧比)検査の統計では、0.9以下を示した方が約38.5%。虚血性心疾患が59.5%で、新規のケースは24.1%もありました。ABIだけでも新規イベントを起こしそうな方がこれだけ出てきます。ABIで値の低い患者さんは、冠動脈を含めた全身の動脈硬化を早期にスクリーニングしていくことが重要です」と強調しました。

セッション3は、康生会武田病院循環器センター・心不全センターの木下法之センター長が、「心不全地域連携とエンレストについて」と題し講演しました。
木下センター長は、ファンタスティック4と呼ばれる心不全の予後改善薬について一つ一つ丁寧に説明し、「心不全治療は、急性期においてはむくみなどの"目に見える治療"として、利尿薬や血管拡張薬、強心薬などを使用しますが、ある程度落ち着くと予後を良くするため、エビデンスに基づく"目に見えない治療"にスイッチしていかないといけません。ARNI、SGLT2阻害薬、β遮断薬、抗アルドステロンなどの予後改善薬治療に早く切り替えることが重要です」と考えを述べました。
また、木下センター長はアドバンス・ケア・プランニングについて、「これは、がん治療だけでなく、心不全治療でも行っていかなければなりません。もしもの時にどうするかを話し合っていくことは、患者さんの満足度向上につながりますし、我々も患者さんの意向に沿ったチーム医療を行うことができます。そこでは、苦しみを取り除く"緩和ケア"のニーズに医療者が一早く気付くことが重要です。緩和ケアは治療からの撤退ではなく、患者さんやご家族のQOLを向上させるアプローチです。我々、専門家である心不全チームは、初期治療から緩和ケアまでコンサルトすることを目標に努力しています」と力強く語りました。

