掲載情報一覧 (2024.6月更新)
2024/06/29 メディア 山科武田ラクトクリニック
○●○●○各種掲載情報●○●○●
■京都新聞 Iru▶miru 掲載記事
※掲載日とタイトルをクリックすることで記事を展開することができます。
 山科武田ラクトクリニック 所長 田巻 俊一
山科武田ラクトクリニック 所長 田巻 俊一
強い精神的ストレスを原因とする心臓疾患「ブロークンハート症候群」をご存じでしょうか?「ストレス心筋症」、あるいは突然発症する胸の痛みや息苦しさ、心電図の変化、心臓の壁運動異常が急性冠症候群(急性心筋梗塞)に酷似しますが、冠動脈に有意狭窄は無く、左室心尖部の収縮不全が進行し、左室収縮末期像がたこつぼに似ていることから「たこつぼ型心筋症」とも呼ばれています。発症メカニズムは未解明ですが、過度のストレスにより、ストレス関連ホルモンの急増が心尖部の微小循環不全や心筋障害を起こすためと考えられています。
閉経後の女性に多く、多くは数日から数週間で回復しますが、一部は心原性ショック、心肺停止、不整脈などをきたす例もあり、軽視できません。私たちの医療機関でも年間数例、胸部症状で緊急受診され、急性心筋梗塞との鑑別のため、冠動脈造影を施行する例を経験します。
我々がストレスを感じるのは、ネガティブな状況、愛する人の死、失恋、別れ、強度の怒り、大事故、自然災害(新潟県中越地震、阪神・淡路大震災、東日本大震災での症例報告があります)、戦争などが大部分と思われます。米国の調査では新型コロナウイルス感染症の流行でブロークンハート症候群が2倍に増加したとの報告もあります。一方、スイスの登録研究ではわずかですが、ポジティブな出来事をきっかけに発症する例もあり、「ハッピーハート症候群」と呼んでいます。あまりにもハッピー過ぎたこと(宝くじ当選、サプライズパーティー、阪神タイガースの優勝、孫の誕生など)でもストレスホルモンのバランスが乱れるのでしょう。
過度なストレスは「こころ」はもちろんのこと「Heart 」も壊すことがあることを紹介しました。ストレスの少ない、こころ穏やかな日々が続くことを「Heart」は願っています。
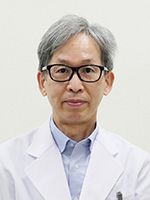 山科武田ラクトクリニック 消化器内科 高橋 周史
山科武田ラクトクリニック 消化器内科 高橋 周史
 山科武田ラクトクリニック 所長 田巻 俊一
山科武田ラクトクリニック 所長 田巻 俊一
普段よく耳にする生活習慣病の一つに高血圧があります。心臓が収縮して血液が全身に押し出される時に動脈の血管壁が押される力を収縮期血圧、心臓が拡張して血管壁にかかる圧を拡張期血圧といいます。血圧測定には診察室で測る「診察室血圧」と家庭で測る「家庭血圧」があり、正確な評価には「家庭血圧」が重視されています。診察室血圧で140/90mmHg以上、家庭血圧で135/85mmHg以上を高血圧とガイドラインで定めています。高血圧の約90%は生活習慣や体質などが原因とされる本態性高血圧です。残りの約10%は腎臓病やホルモン異常などの病気が原因となる二次性高血圧で、病気が治ると改善します。一般に血圧は1日では朝に、1年では寒い冬に高くなります。高血圧は自覚症状がないことが多く、知らないうちに心臓や血管に大きなダメージを与え、気が付いたら、狭心症・心筋梗塞、心不全、脳卒中、腎不全など重篤な病気になっていたという事態を招きます。高血圧が別名「サイレントキラー(静かなる殺人者)」と言われる理由です。
時折、有名人が「急性大動脈解離」で亡くなられたとの報道にふれることがあります。この「急性大動脈解離」も高血圧の合併症の一つです。大動脈は外膜、中膜、内膜の3層構造となっていますが、なんらかの原因で内膜に裂け目ができ、中膜の中に血液が入り込んで長軸方向に大動脈が裂ける病気です。特に60歳以上の男性に多く、一部はMarfan症候群など遺伝性疾患で起こりますが、高血圧と密接に関連しています。突然、胸あるいは背中に杭が刺さるような激痛が起こり、胸から腹、さらに脚へと下向きに移って行くのが特徴です。裂けた箇所や進展によって心臓、脳、腸管、腎臓、下肢などの虚血症状を引き起こし、突然死も起こりうる急性期予後不良な疾患です。
このような合併症を起こさないために高血圧を侮ってはいけません。毎朝、目覚めたら、朝食までの間に2度「家庭血圧」を測定しましょう(可能なら朝と晩)。高血圧の予防と治療への第一歩です。
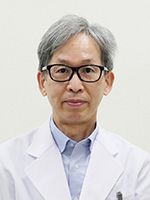 山科武田ラクトクリニック 消化器内科 高橋 周史
山科武田ラクトクリニック 消化器内科 高橋 周史
 山科武田ラクトクリニック 所長 田巻 俊一
山科武田ラクトクリニック 所長 田巻 俊一
心臓突然死を防ぐには、最も多い原因疾患といわれる心筋梗塞・狭心症の予防が非常に重要です。心臓の栄養血管である冠動脈が、動脈硬化で狭窄することにより心筋が酸素不足になるのが狭心症です。また、血管壁に蓄積したコレステロールを含むプラーク(盛り上がった病変)が破綻することでできた血栓が血管を閉塞すると、急性心筋梗塞を発症し、激しい胸痛が持続します。心臓病が日本人の死因の第2位になって久しいですが、その大部分がこの疾患の増加によります。発症は突然でも、その基盤となる動脈硬化は、長い間の生活習慣の積み重ねによることが多いのです。生活習慣の乱れから、内臓脂肪増加、高血圧、糖尿病、脂質異常症などいわゆる生活習慣病が起こり、動脈硬化が進行、ある日突然心筋梗塞や脳卒中の発症に至る一連の流れは、ドミノ倒しに例えて「メタボリックドミノ」と呼ばれています。このドミノ倒しの進展を出来るだけ早い時期に止めること、すなわち食べ過ぎ、飲み過ぎ、塩分過多、運動不足(特にコロナ時代)、喫煙などの日常生活習慣の乱れを改善し、心臓病のリスクとなる生活習慣病(「隠れ心臓病」)に陥らないように日々取り組むことが大切です。「ローマ(健康)は1日にして成らず」のごとく、継続が必須です。また定期的に健診や人間ドッグを積極的に活用し、ご自身の生活習慣病やその傾向=「隠れ心臓病とその予備群」の有無を把握することも有用でしょう。自覚症状がなく、日常生活に支障がなくても指摘された「隠れ心臓病と予備群」は放置せず、心臓突然死に見舞われないために適正な精査や必要な治療を受けて下さい。また、胸の痛み、動悸、息切れなど心臓に不安がある場合には、出来るだけ早く、専門医療機関できちんとした検査を受けましょう。2月1日から山科駅前に移転した当クリニックでも循環器病の診療を継続しています。お気軽にご相談ください。
山科武田ラクトクリニック 所長 田巻 俊一 
健康だった人が、ある日突然、命を落とす。ゴルフのプレー中に倒れ不帰の人となったとか、会議中に急死したなど皆様の周囲でも耳にされることがあると思います。
いわゆる「突然死」は予期しない急死のことで、発症から24時間以内の死亡と定義されています。原因は心筋梗塞50-60%をはじめ、心筋症30-35%、遺伝性不整脈10%など心臓病によるものが大半を占め、そのほとんどが「心室細動」と呼ばれる致死的な不整脈に起因するといわれています。「心室細動」になると心臓は震えるのみで血液を送り出せなくなる心停止の状態です。数秒で意識を失い、数分で脳をはじめとした全身の細胞が死んでしまいます。日本ではなんと1年で約7.9万人、1日で約200人が心臓突然死で亡くなっています。それでは、このような状態に遭遇したら、どうしたら良いのか?
「心室細動」からの救命には迅速な心肺蘇生と電気ショックが必要です。電気ショックが1分遅れるごとに救命率は10%ずつ低下します。119番通報をしてから救急隊が到着するまでの平均時間は9.4分、救急隊や医師を待っていては命を救うことができません。その場に居合わせた「われわれ」が協力し合い、119番通報と同時に、勇気を奮って、直ちに胸骨圧迫(心臓マッサージ)を開始し、AED(自動体外式除細動器)を使用することが救命への一歩となります。胸骨圧迫は胸骨の下半分のところを、5cm沈むくらい、1分間100―120回のペースで圧迫します。AEDは医療機関以外にも学校、市役所、公民館、駅、スポーツセンター、商業施設、コンビニ、ドラッグストアなどで設置されています。自宅や勤務先の付近でAEDの設置場所を確認しておくと良いでしょう。AEDの使い方や一次救命処置の技術を学ぶ講習を地域の消防署で受ける事ができます。AEDを用いた救命処置で突然の心停止の約半数の人が救われます。ひとりでも多く突然死から救うために、AEDの使用が当たり前となる社会をめざしたいものです。
※医師やスタッフの肩書き/氏名は掲載時点でのものであり、現在は変わっている可能性があります。
