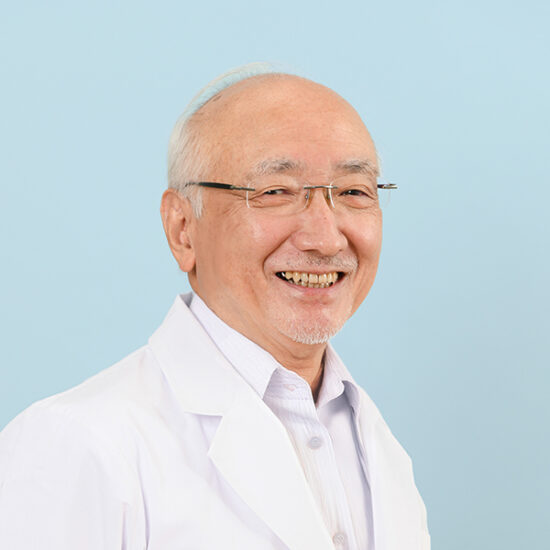
田巻 俊一
- 顧問
循環器センター(循環器内科)は、循環器の血管内治療を主な領域としています。
高度な治療方法が確立されているので、当センターでは「いかに患者さんのご負担を減らすことができるか」に集中しています。
循環器分野は生活習慣と密接な関わりがあるので、患者さんと一緒になった治療が大切です。
何より「患者さんに優しい治療」となることを心がけています。
このほか適用例では、検査・治療に炭酸ガス造影を導入することで、造影剤による身体へのご負担を減らす取り組みも行っています。
循環器センターは、急性心筋梗塞や狭心症などの冠動脈疾患、急性ならびに慢性心不全、大動脈弁狭窄症や僧帽弁閉鎖不全症などの心臓弁膜症、大動脈解離や大動脈瘤などの大動脈疾患、末梢動脈疾患、静脈疾患など、心血管疾患の診断と治療に対応しております。
当院では、心不全センター・不整脈治療センター・心臓血管外科を併設し連携をとりながら専門性の高い治療を行っています。
| 心臓疾患 | 急性冠症候群(急性心筋梗塞・不安定狭心症)、狭心症、心臓弁膜症、心筋症など | |
|---|---|---|
| 血管疾患 | 動脈疾患 | 下肢閉塞性動脈硬化症LEAD(Lower extremity arterial disease)、急性下肢動脈閉塞ALI(Acute Limb Ischemia)、大動脈解離・大動脈瘤など |
| 静脈疾患 | 下肢静脈瘤、深部静脈血栓症、肺塞栓症(急性・慢性)、肺高血圧症など | |
| 心不全 | 急性心不全・慢性心不全 | |
| 高血圧 | 高血圧性心疾患 | |
| 脂質異常症 | 高脂血症、家族性高コレステロール血症など | |
急性心筋梗塞とは、冠動脈閉塞のため心筋への血液の供給が途絶え、心筋が酸素の供給を受けられずに心筋細胞が壊死する病気です。緊急入院・緊急心臓カテーテル治療が必要になります。
| 症状 | 胸の強い痛みや圧迫感が出現し持続します。症状は激しく長く続き、ニトログリセリン舌下錠を使用しても軽減しません。死の恐怖を伴う事があります。 一部の人では胸痛がみられない(無症候性心筋虚血)こともあります。 |
|---|
冠動脈狭窄により心筋への血流が減少し、主に階段を登るなどの運動時に胸部症状が生じる疾患です。
| 症状 | 胸の圧迫感や締め付け感、痛みが生じます。肩や左腕、頚部、奥歯へも広がることがあります。労作性狭心症では、早歩きや階段昇降などの労作によって症状が生じ、安静にすると治まります。食後や寒冷時などに症状が出現、増悪することがあります。 糖尿病のある方や高齢の方では、上記の典型的な症状に乏しいことがあります。また、冠動脈に狭窄があり虚血が生じても症状を認めない場合、無症候性心筋虚血と呼ばれます。この場合も治療の対象となります。 |
|---|
下肢閉塞性動脈硬化症(LEAD)は、下肢の動脈が狭窄・閉塞し血行が悪くなる病気です。症状は進行に応じて無症状から、間欠性跛行、安静時痛、潰瘍、壊疽へと進行します。
下肢閉塞性動脈硬化症LEADの症状は、進行の程度によって4段階に分けられます。(フォンテイン分類)
| Ⅰ度(無症状) | 足のしびれや強い冷えを感じる程度、皮膚も青白くなっている。 |
|---|---|
| Ⅱ度(間欠性跛行) | 少し歩くと足が痛くなり歩けなくなるが、休むとまた歩けるようになる。通常はふくらはぎが痛む。 |
| Ⅲ度(安静時痛) | 足の痛みが強くなり、夜も眠れなくなる。足が黒く変色し、深爪や小さな傷が治りにくくなってくる。 |
| Ⅳ度(潰瘍・壊死) | 足先に血液が届かなくなり、つま先やくるぶしの外側などに、傷をきっかけにしてただれや潰瘍ができてくる。重症になると壊疽を起こし、切断に至ることもある。 |
急性下肢動脈閉塞ALIは、下肢の動脈が突然閉塞して起こる、急性の血行障害です。下肢の血流が急激に減少することで、虚血(酸素と栄養が下肢に不足すること)が進行し、組織が壊死に陥る可能性があります。
急性下肢動脈閉塞ALIは、緊急性の高い疾患であり、早期の診断と適切な治療が重要です。放置すると、四肢切断や生命の危険につながる可能性があります。
急性下肢動脈閉塞ALIの症状としては、急な下肢の疼痛、蒼白、脈拍消失、冷感、知覚鈍麻、運動麻痺(6Ps)などが挙げられ、原因としては、塞栓症(血栓が血管を詰まらせること)、血栓症(血管に血栓が形成されること)、外傷などが考えられます。
心臓の内部は4つの部屋に分かれています。各部屋は一方通行で逆流しないよう、部屋と部屋の間には弁と呼ばれる扉が4つあります。このうち、左心室と大動脈の間にある弁を大動脈弁と呼びます。
大動脈弁膜症はこの弁の働き不十分になることで起こる症状で下記の疾患があります。
| 大動脈弁狭窄症 | 何らかの原因で大動脈弁の動きが悪くなるときちんと開かなくなり、左心室から大動脈に血液が送り出しにくくなります。 その結果、左室に大きな負担がかかるようになり、進行すると心不全を引き起こします。 |
|---|---|
| 大動脈弁閉鎖不全症 | 大動脈弁の閉まりが悪くなり、心臓から大動脈に押し出された血液が再び左心室内に逆流する病気です。押し出した血液が戻ってくるため心臓にとって大きな負担となり、呼吸困難などの心不全症状が出現する場合があります。 |
心不全とは、心臓が悪いために息切れやむくみが起こり、だんだん悪くなると生命を縮める病気です。身体を動かす時に起きる息切れが、だんだんと安静時にも生じるようになり、疲れやすさや下腿のむくみを伴うことがあります。
| 症状 | 疲れやすい、歩くなど軽い労作で息切れがする、横になると呼吸が苦しく、また特に朝方息苦しくなる、足がむくむ、などの症状が認められます。 |
|---|---|
| 原因・病態 | 心筋梗塞などの虚血性心疾患・心筋症・心筋炎などによる心臓の収縮力の低下や、高血圧・弁膜症・貧血などによる心臓への負荷の増大、徐脈性または頻拍性不整脈など、さまざまな原因により心臓のポンプとしての機能が低下した状態を表します。身体に必要な酸素が足りなくなり息切れがしたり疲れやすくなる、下肢のむくみや肺などの臓器に水分がたまり様々な症状を起こします。 |
下肢静脈瘤とは、脚の静脈が拡張し、瘤のように浮き出た状態を指します。
主な症状は、ふくらはぎの怠さや重さ、むくみ、夜間のこむら返りなどです。放置すると、皮膚炎、色素沈着、潰瘍、出血などの合併症が起こる可能性があります。
| 見た目 | 静脈の血管が「ぼこぼこ」と浮き出る |
|---|---|
| ふくらはぎ | だるさ、重さ、痛み |
| 足 | むくみ、冷え、ほてり |
| 夜 | こむら返り(足のつり) |
| 皮膚 | 湿疹、かゆみ、色素沈着、潰瘍、出血 |
| その他 | しびれ、疲れやすさ |
主な症状は、下肢のむくみ・痛み、皮膚の色調変化、圧痛などです。特に片方の脚に症状が出ている場合は注意が必要です。また、無症状の場合もあります。
| 下肢の腫れ | 特にふくらはぎや太ももにむくみが見られます。 |
|---|---|
| 痛み | ズキズキとした痛みが感じられることがあります。 |
| 皮膚の色調変化 | 赤黒く変色したり、茶色く色素沈着したりすることがあります。 |
| 圧痛 | 圧迫すると痛みが感じられることがあります。 |
| 呼吸困難、胸痛 | 血栓が肺に移動して肺塞栓症を起こすと、息苦しさや胸痛などの症状が出ることがあります。 |
肺塞栓症は、静脈を流れてきた塞栓子(血栓、脂肪、空気、腫瘍など)が肺動脈を閉塞することにより生じる肺循環障害です。
肺塞栓症の症状は、突然の呼吸困難や胸痛、息切れ、咳、血痰などです。まれに、冷や汗、動悸、失神、下肢の腫れや痛みなどの症状も見られることがあります。重症例では、心臓に負担がかかり、意識が低下したり、気を失ったりすることもあります。
重症で救命が困難である症例もあり、早期の診断及び治療が重要であるとされています。通常、肺塞栓症は急激に発症する急性の経過をたどることが多いですが、少しずつ血栓が肺動脈に詰まっていく慢性肺塞栓症もあります。
肺高血圧症は、いわゆる高血圧症とは異なり、心臓から肺に血液を送る血管である“肺動脈”の血液の流れが悪くなることで、肺動脈の血圧が高くなる病気です。肺動脈の血圧が高くなると、心臓に負担がかかり、息切れやだるさ、足のむくみ、失神、喀血といった症状が出るようになります。
安静時の平均肺動脈圧が20mmHg以上(労作時では30mmHg以上)となったときを肺高血圧と呼びます。
| 症状と原因・病態 | 肺高血圧症を来たすと肺動脈に血液が流れにくくなるため、心拍出量(心臓が1分間に送り出す血液の量)が低下します。そのため全身の組織への酸素供給低下を招き、運動時の呼吸困難感、疲れやすい感じ、動悸などの症状を生じます。 また、さらに病状が進行すると、肺動脈圧が高くなった肺の血管に血液を送り出すだけの力を心臓が出せなくなってしまい、心不全の状態に至ります。心不全になると腹水や下肢の浮腫を生じます。また、重症の肺高血圧症では喀血や失神を来たすこともあります。 |
|---|
チーム医療で患者さんを支えます
インフォームドコンセントの充実と診療・治療の標準化を目標としています。
急性心筋梗塞および狭心症の患者さんには心臓カテーテル検査・治療のクリニカルパス使用を積極的に進めています。
クリニカルパスの運営においては、医師・看護師・薬剤師・理学療法士・臨床工学技士・放射線技師・管理栄養士・患者サポートセンターなどと連携し、患者さん一人ひとりに対応しています。さらに毎月、循環器ワーキンググループを開催し、クリニカルパスの改善・更新、そして新規作成のミーティングを行っています。
地域の先生方と連携し健康増進に努めます
当センターは京都の中核病院として、今後も増加すると予想される「虚血性心疾患(急性冠症候群、狭心症など)」を中心とした循環器疾患の患者さんの診療に日々努力しています。
的確な診断と治療技術を積極的に取り入れると同時に、患者さん本位の思いやりのある医療を心がけています。
増加が予想される患者さんに対し、当院だけで出来ることは限られています。
術後・退院後は地域のかかりつけの先生(開業医の先生)の力が重要となります。
特に循環器疾患は生活習慣病が原因なので、いかに再発を予防していくか、長期間の支えが必要です。
地域医療支援病院として、かかりつけの先生方と一緒になって患者さんの健康増進に努めたいというのが私たちの望みです。
| 生理機能検査 | 心臓エコー検査 | 6,799件 |
|---|---|---|
| 下肢血管エコー検査 | 1,803件 | |
| トレッドミル負荷心電図 | 61件 | |
| 心臓カテーテル検査 | 669件 | |
| 経皮的冠動脈形成術(バルーンおよびステント留置術) | 362件 | |
| ロータブレーター | 13件 | |
| 経皮的末梢血管形成術 | 58件 | |
| エキシマレーザー冠動脈形成術 | 29件 | |
| 緊急冠動脈インターベンション | 61件 | |
| 心・血管カテーテル総数 |
739件 |
|
急性冠症候群(急性心筋梗塞、不安定狭心症)は、発症すると急速に危険な状態になることが多いです。このため当院では、循環器内科医師が24時間体制で常駐しており、迅速な診断・適切な治療に努めています。
特に急性冠症候群などの急性期心疾患の治療にあたっては、24時間体制で緊急心臓カテーテル検査が出来るようにしています。
(循環器内科緊急オンコール医師1名、臨床工学技士、放射線技師、看護師とも連携して万全の体制を整えています)
原則として急性冠症候群には経皮的冠動脈形成術(PCI)を緊急で行い、生命の危険を回避するだけでなく、患者さんの術後の改善・生活の質の向上に努めています。
一旦心筋壊死に陥ってしまうと回復は極めて困難です。このため急性心筋梗塞では、1分1秒でも早い再灌流療法が必要になります。
急性心筋梗塞の患者さんが来院されてから緊急心臓カテーテル検査のための動脈穿刺までの時間は60分以内、来院からバルーンによる再灌流までの時は90分以内であるべきとガイドラインで勧告されています。
全例(休日・夜間を含めて)が目標時間内に治療を開始出来るよう、さらに研鑽を積み重ねて迅速な診断と治療を臨床工学技士、看護師とともに連携し向上させたいと考えています。
当院では、従来からの心エコーや運動負荷心電図の他、マルチスライスCT(320列 MDCT)、心臓MRIなどが検査でき、当院に併設されている画像診断センターでは糖代謝をイメージングできるPET-CTも検査可能です。これらの検査を駆使して簡便で詳細な狭心症の診断や病態評価が可能となっています。
当院は3つのカテーテル検査室があり、バルーン拡張術、ステント留置術、血栓吸引、ロータブレーター(高速回転ドリル)、エキシマレーザーによる治療が可能です。
治療の中心となるステントは、従来では金属のコイルを血管内に留置するものでしたが、最近の薬剤溶出ステントは金属コイルに再狭窄を予防する薬剤を含む特殊なポリマーが接着されています。ポリマーから徐々に薬剤が溶出し、ステント内の再狭窄を予防します。
従来は1/3もの頻度でステント内再狭窄が発生していましたが、この薬剤溶出性ステントによって再狭窄はまれになりました。
さらに、再狭窄の可能性が高い透析患者さんや糖尿病患者さん、そして冠動脈バイパス手術の適応患者さんにも積極的にステント治療が行えるようになりました。
当院では、患者さんに対してやさしい経皮的冠動脈形成術(PCI)を心がけております。
カテーテルの検査や治療は術後の安静が苦痛であるというイメージがありますが、手首や肘から検査および経皮的冠動脈形成術(PCI)を行うことにより、治療後も検査室から歩いて病室に帰っていただくことが可能です。
治療用カテーテルを従来よりもさらに細いカテーテルを用いることにより、患者さんに負担が少ない心臓カテーテル検査・治療を試みています。
今尚6Fr~7FrサイズのガイドカテーテルによるPCIが一般的ですが、当院においてはさらに細い5FrサイズのガイドカテーテルによるPCIが増えています。その他6Frシースレスガイドカテーテル(4Fr相当)によるPCI、4FrガイドカテーテルによるPCIや3Fr診断カテーテルによる検査など、より低侵襲な検査・治療も積極的に行っています。
冠動脈を形態学的に観察する方法として、1990年代から血管内超音波(IVUS)が広く用いられるようになり、IVUSから得られた情報を基に、経皮的冠動脈形成術(PCI)の施行が実施されています。
最近では、超音波の代わりに近赤外線を用いて冠動脈を観察する光干渉断層法(OCT)が開発されました。OCTはこれまでにない高い画像分析能を有することから、新しい冠動脈の画像診断装置として期待されています。
当院でも導入し、実臨床の場で有用な診断装置として汎用しています。冠動脈の内膜側の詳細な評価が可能であり、今までIVUSだけでは分からなかったステントの圧着不良や血栓、解離などの所見が明瞭に分かるようになりました。
OCTの所見や情報については、当院からも情報発信していければと考えています。
冠動脈治療の成功率は一般的に約98%と言われています。しかしながら、約10%の方々は再び動脈硬化が進行し「再狭窄」してしまいます。
これまで再狭窄に対してあらゆる手段を用いて、再発率を最小限に抑える努力をしてきました。今、そのような再狭窄を繰り返す動脈硬化に対しての最新の治療として「エキシマレーザー冠動脈形成術(ELCA:Excimer Laser Coronary Angioplasty)」が注目されています。
この治療は、平成24年4月に新規で保健償還が認められ、同時にこの治療を行うための施設基準が新たに設けられました。当院でもこの施設基準に認められ、エキシマレーザー装置を導入し治療を行っています。
このエキシマレーザーを使用することにより、心筋梗塞の根本的原因となる動脈硬化をレーザーによって蒸散させ取り除くといった今までとは全く異なる新しい方法で治療を行うことができ、動脈硬化が再びできるのを防ぐことが期待できる画期的な治療法です。また、このエキシマレーザーは急性心筋梗塞にも効果を発揮するといわれており、今後さまざまな治療に活用出来ることが期待されます。
血管の内壁にできるコブで血栓の原因になります。
プラークは、コレステロールが原因で血管の壁にできるコブです。プラークがあると、さらにプラークがたまったり、粥状の脂質がたまったりします。血管を詰まらせる原因となるので、早期に取り除かなければなりません。
原因の多くは「生活習慣病」です。糖尿病、コレステロール血症、あと高血圧だとか高尿酸血症、そして喫煙ですね。一番の原因はコレステロールです。
血管にカテーテルを入れて治療します。
血管内にステントを入れて治療をします。プラークが飛び散り、末梢血管を詰まらせることのないようレーザーで蒸散したり、カッターで破砕しゴミを回収するなど、様々な治療を行っています。
いずれも、血管にカテーテルを挿入して治療を行うので、患者さんへのご負担が少ない優しい治療です。
遺伝性のコレステロール血症があります。
「家族性高コレステロール血症」という遺伝性の病気があります。これまで、治療方法がなく難渋していましたが、ようやく治療薬が出てきました。
とは言え、発見・治療が遅れると、若年性心筋梗塞や狭心症になる可能性があります。病気だと自覚されていないケースが多いので、是非、ご相談下さい。早めにコレステロールをコントロールすることが大切です。
施術後も健康管理を続けることが大切です。
治療した血管は良くなっても、他の場所で血管が詰まることが多くあります。原因は生活習慣病なので、施術後は、高コレステロール、高血圧、糖尿などにしっかりと対応していくことが重要です。
かかりつけとなる地域の開業医の先生と連携をとり、皆さんの健康増進に努めています。
循環器センター・心不全センター・不整脈治療センター 3科のチーム医療
心血管治療チーム 特設サイトもご覧ください。
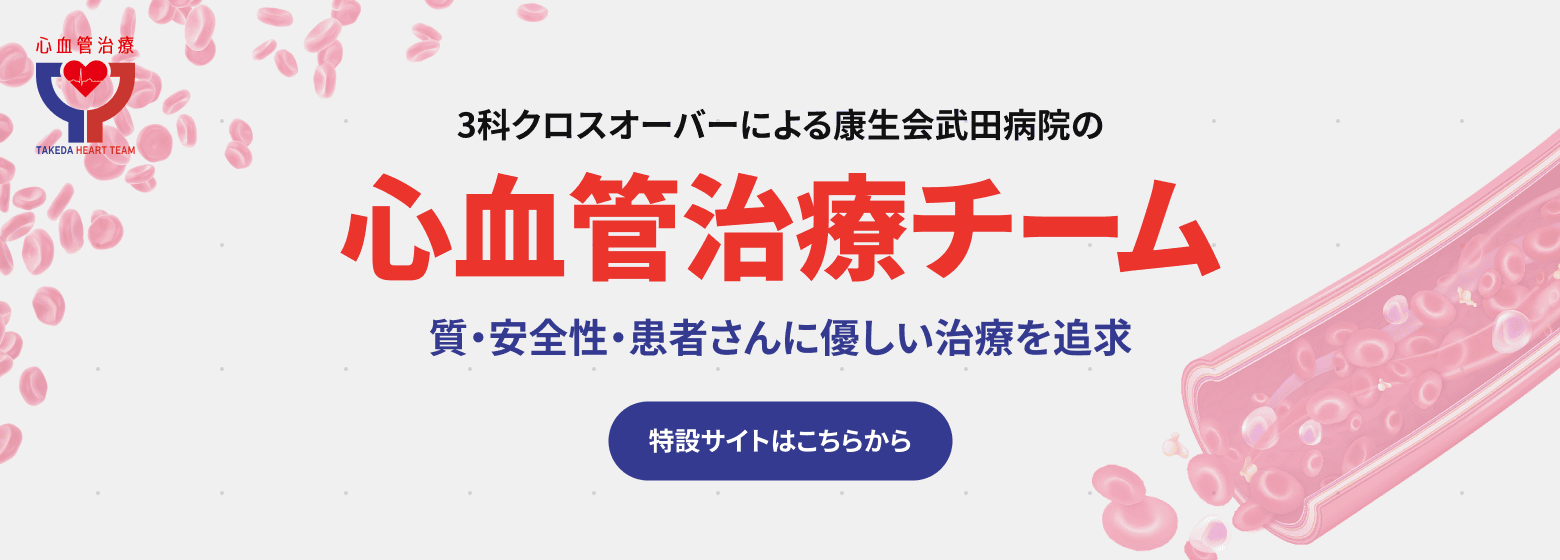
診療時間
9:00〜12:30
受付時間 8:00~12:00
14:00〜16:00
受付時間 13:00~16:00
日曜・祝日・
年末年始(12/30~1/3)
※急患は24時間受付
※診療科によって異なります。診療担当表をご参照下さい。
診療予約
受付時間 9:00~17:00(日・祝日除く)
お困りごとはありませんか?
メニューを閉じる